あえばさんのブログです。(※ブログタイトルはよろぱさんからいただきました)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
トンデモ本かと思って手に取ったらやっぱりトンデモだったー!
僕は生物の専門ではないので(高校の「生物」すら習ってない)不明な点も多いが、わかる範囲内だけでも誤りや突っ込みどころ多数。
ダーウィニズムを否定するというのだからどんなものかと思ってみたら……。
経歴を見ると医学博士。生物学者ですらない。
いやまて、偏見やレッテル貼りはよくない。
一つ一つ丁寧に疑問点や批判点を挙げておこう。
まず、第1章。
アザラシにひれはどうしてできたかという問題について二つのシナリオを紹介している。
ここからいきなり疑問符が浮かぶ。
ダーウィニズムは必ずしも突然変異ありきではない。
②のように、まず環境の激変があり、自然淘汰によってアザラシ的な哺乳類が生き延びた、というシナリオも考えられる。
地理の隔絶が種分化を促すというのはダーウィニズムの基本の一つだ。
ダーウィニズムとラマルキズムの違いを示す例としては不適当すぎる。
以後も著者は何度かダーウィニズムに喧嘩を売るが、いずれも自然淘汰のことがすっぽり忘れ去られ、突然変異のことしか頭にない。
ダーウィニズムには自然淘汰という概念もありましてね?
読んでいると、どうにも突然変異というものを、一世代でまったく異なる環境に完全に適応できるほどの大きな変異であると勘違いしている節がある。
あー、ドーキンスもそういう勘違いしてる人がいるって批判してたなあ……。
実際には、進化に関わるような突然変異は逆説的に非常に小さなものでしかあり得ない。
ちなみに第1章のタイトルは『「突然変異」と「自然淘汰」で進化は説明できない』。
あのー、「自然淘汰」はどちらへ?
「次々に修復」と当たり前にいっているが、どのようなメカニズムで修復されたと思っているのか。
なんでさっきから自然淘汰のこと無視するん?
後者は賛成だが、そんな当たり前のことをなにドヤ顔で……。
この時点で読むのをやめてもよかったのだが、逆に面白くなってきたので続けよう。
地球上のすべての生物にはDNAという共通する要素がある。
植物だろうが動物だろうが地球外生命体だろうが適用できる普遍性こそがダーウィニズムだ。
特定の種類の動物、この著者が取り上げるのは脊椎動物だが、それだけの進化を論じても、じゃあそれ以外の生物はどう説明するの? という話になる。
もちろん本書はその点について黙して語らない。
くわしくは著者の具体的な実験と説を見て考えよう。
第2章ではサメについての実験が紹介されている。
サメを麻酔海水につけるとのたうち回って陸上に逃げるらしい。
のたうち回ると血圧が上がり、エラで空気呼吸ができるようになる。
何回も繰り返すと、最初は20分で息絶え絶えだったサメが、1時間陸上に放っても平気になる。
エラの一部が袋状になって肺になるのは時間の問題である。
ヒトも、はじめは1分息を止めるだけで苦しそうにするが、訓練次第で5分は止められるようになる。やがて息をしなくても生きられるようになるのは時間の問題である。
馬鹿な。
本気で正気を疑った。
いや、本文に書いてあるのはもちろんサメのくだりだけね。
他にも血流が多いと肝臓に埋め込んだ軟骨が硬骨になってしまうんだとか。
専門的なことはよくわからないけれど、要約すると訓練次第でサメが哺乳類的なものを獲得するんだと。
なるほど、それは興味深い実験ですね。
で、それが進化とどう関係するんで……?
で、次章にてようやく個体の変化が次の世代に伝わるメカニズムが語られるらしい。
重要なのはそこですから。混乱を避けるために触れなかった?
触れなかったせいで混乱しました!
いったいどんな読者を想定しているのやら。
第3章。
いったいどんなメカニズムが語れるのかな。ワクワク。
? ……?? ……!??
さっぱりわからん。
わからないなりに要点だけかいつまむと、「獲得形質の遺伝」についてはさすがの著者でも否定するらしい。
だが、「行動様式」が伝われば遺伝によらずとも獲得形質は次代に伝わる。
なるほど、つまりはミームというわけか。
子が親の行動を真似るというのは人間にかぎらず様々な動物でも観察できる。
つまりだ。あるサメがのたうち回って1時間陸上で生きられるようになった!
その子も親の真似をして1時間陸上で生きられるようになった!
さらにその子も親の真似をして1時間陸上で生きられるようになった!
さらにさらに(ry
で、いつになったらサメは陸上に進出できるんですかね?
「行動様式」が伝わってもそれは0からのスタートでしょ? 強くてニューゲームちゃいますやろ? 「次の世代」には伝わるかも知れないけど「次の次の世代」にはどう伝わるんです? 同じようにしか伝わりませんよね? 繰り返すうちに2時間陸生できるようにはなりませんよね? それとも僕がなにか読み違いしてるんですか?
……なにがなんだかわからない。
続けて「ワイスマン実験」批判。これもまるで意味がわからない。
ワイスマン実験とは、獲得形質の遺伝を否定したとされる有名な実験で、22代・1600匹のネズミの尾を切り続け、それが次代に遺伝しないことを証明した実験だ。
著者はこの実験を「二重の意味で愚か」であると批判している。
まず①だが、ラマルクについては僕も詳しくないのでなんともいえない。
だが、ワイスマンがラマルクを誤解していたからといって実験結果が変わるわけではない。
「獲得形質の遺伝の否定」、ワイスマン実験の意味はそれだ。
この点については、著者も「獲得形質が次代に遺伝することはあり得ない」(p.106)ハッキリ書いている。
ちなみに第3章のタイトルが『「遺伝」によらずとも変化は次代につながる』だ。
著者はなぜワイスマン実験を否定したかったのだろう。
著者の主張とワイスマン実験は別に矛盾しないはずだ。
実験は正しいがこんな実験に意味はない! とでもいいたいのだろうか?
そして②について。
サメにとっても麻酔海水に浸けられるのはただの災難でしかないだろうに。
なになに、サメは陸上にあがって1時間も無事でいられる形質を獲得した?
では、獲得形質と怪我をどう区別するのか。
わかりやすいようヒトの例で考えよう。
筋肉トレーニングとは、人為的に筋肉を痛めつける行為だ。
痛めつけられることで超回復が起こり、何度も繰り返すうちに筋肉が肥大化する。
これを「獲得形質」であると定義することには著者も納得してくれるだろう。
では、もう一例。事故によって指がごっそりもげた。
放っておくと、皮膚が傷口を覆うように再生し、指は短くなったが傷口はふさがった。
さて、筋トレと怪我の再生との差異はなにか。
怪我が起こり、それが回復した。どちらも同じことだ。
前者は結果的に肥大化し、後者は指が短くなった。
その違いはあるが、両者をどう区別するのか。
尻尾を切られたマウスでも同様のことが起こったはずだ。
傷を再生し、なんらかの形質を獲得したはずだ。
視点を変えよう。
サメはなぜ陸上でも1時間生きられる形質を獲得できたのか。
著者は「ウォルフの法則」を根拠に「当然」だとしている。
機能が変わると、形もその機能の変化にしたがって変化する。
いや、それこそ経験則ですやん。
ダーウィニズムを「論」にすぎず、「法則」にはほど遠いと批判しておきながら「ウォルフの法則」という経験則にすぎないものを支持するとはいやはや。
ダーウィニズム的に答えるならこうだ。
陸上に打ち上げられるような経験は滅多にないが、何度も起こるようならその環境にある程度適応できた方が生存に有利だったからだ。
筋肉トレーニングもそうだ。痛めつけるほど何度も使う部位なら、超回復により肥大化させた方がいい。その方が明らかに生存に有利だ。
これが突然変異と自然淘汰によって生まれたシステムだ。
まとめよう。
この著者はいったいなにが主張したいのか。
まず本書のタイトルにある「重力」。
本記事ではここまで無視してきたが、もちろん本書では重力と進化の関係について様々な例を書いている。
たとえば、重力によって個体の骨格や形が変化して「ほら、ホヤの幼生が魚っぽくなるでしょ?」というような例が紹介されていたりする。
サメの例も、水の中から陸上に上げられ見かけ上重力が6倍になったことへの適応だとしてしている。
が、そもそも獲得形質が遺伝しないことには進化とは関係しようがない。
よってこの記事では無視してきた。
進化とは無関係のレベルでしか「重力」は扱われていないからだ。
仮に重力が進化に関わるなら、重力はすべての生物に平等にかかる力であるため、生物の多様性が説明できない、という反論もできる。
また、著者がダーウィニズムを否定する論拠としては、①突然変異体はふつうすぐ死ぬ、②著者の貧弱な想像力では進化に関わるとは思えない、という二点である。
いずれもダーウィニズムを根本から誤解しているのと、自然淘汰のことをすっぽり忘れているにすぎない。
そして「我々は遺伝子を過大評価しすぎてきた」というようなことも書いている。
遺伝によらずとも、行動様式が伝わることで形質もまた次代に伝わることがある。
だが、次の次の世代にどのように伝わるのかについては本書は黙して語らない。
以上、非常にキチガイじみていて面白い本でした。
できるかぎり本書の狂気を伝えようと長々と書きましたが、これだけだとなにがなんだかわからないことでしょう。
そういう方は自らの手で本書を手に取ってみるのはいかがでしょうか。
きっとなにがなんだかわからないはずです。
生物は重力が進化させた (ブルーバックス)
こんなトンデモ本読んでられるか! 俺はまともな進化生物学へ帰る!
という方は、以下の本がオススメです。
利己的な遺伝子 <増補新装版>
盲目の時計職人
進化の存在証明
僕は生物の専門ではないので(高校の「生物」すら習ってない)不明な点も多いが、わかる範囲内だけでも誤りや突っ込みどころ多数。
ダーウィニズムを否定するというのだからどんなものかと思ってみたら……。
経歴を見ると医学博士。生物学者ですらない。
いやまて、偏見やレッテル貼りはよくない。
一つ一つ丁寧に疑問点や批判点を挙げておこう。
まず、第1章。
アザラシにひれはどうしてできたかという問題について二つのシナリオを紹介している。
著者は、①がダーウィニズムで②がラマルキズム、両者は決して相容れない説だとしている。①海付近で生活していたグループの中で、突然変異によりひれに近いなにかが発生した。彼らは海という未開拓のエリアで生活できるという利点を獲得したためにより繁殖し、だんだんひれが発達した。
②なんらかの地殻変動が起き、哺乳類グループの生息していた地域が海になった。多くは死んだが、一部が浅瀬を見つけて生き延び、試行錯誤のうちに魚を捕らえることを覚えて生き延びた。
ここからいきなり疑問符が浮かぶ。
ダーウィニズムは必ずしも突然変異ありきではない。
②のように、まず環境の激変があり、自然淘汰によってアザラシ的な哺乳類が生き延びた、というシナリオも考えられる。
地理の隔絶が種分化を促すというのはダーウィニズムの基本の一つだ。
ダーウィニズムとラマルキズムの違いを示す例としては不適当すぎる。
以後も著者は何度かダーウィニズムに喧嘩を売るが、いずれも自然淘汰のことがすっぽり忘れ去られ、突然変異のことしか頭にない。
ここでちょっと考えていただきたい。突然変異というのは、いいかえれば奇形である。奇形の子どもが突然生まれても、親がうまく育てられずに死んでしまうか、あるいははなから見放されてしまうかであることは、犬や猫を飼った経験のある方はよくご存じだと思う。こんなことで本当に進化が起こるのだろうか。(p.31)
進化をダーウィニズムで説明するならば、代謝のシステムが変わるという生物にとってこの上なく重大なことが、突然変異で起こることになってしまうのである。代謝の変化が突然変異で起こるメカニズムを想像することは不可能である。(p.72)
いや、あんたそりゃ、突然変異だけじゃ説明できるわけありませんって。突然変異がおきて軟骨が硬骨になる。しかし、なぜこんなに目的にかなって変化が起こるような突然変異が発生するかということについては、ダーウィニズムは黙して語らない。(p.74)
ダーウィニズムには自然淘汰という概念もありましてね?
読んでいると、どうにも突然変異というものを、一世代でまったく異なる環境に完全に適応できるほどの大きな変異であると勘違いしている節がある。
あー、ドーキンスもそういう勘違いしてる人がいるって批判してたなあ……。
実際には、進化に関わるような突然変異は逆説的に非常に小さなものでしかあり得ない。
ちなみに第1章のタイトルは『「突然変異」と「自然淘汰」で進化は説明できない』。
あのー、「自然淘汰」はどちらへ?
はい、それが自然淘汰ですね。たとえ突然変異が起こったとしても、形質の変異に結びつくようなことはほとんどありえないという実例を紹介しよう。1986年に起きた旧ソ連のチェルノブイリ原発事故を覚えておられるだろうか。(中略)強い放射線にさらされているネズミには、一年間で一億年分くらいの突然変異が現実に発生しているが、これらは次々に修復されて、このネズミはまったく普通に生活しているという。(p.34)
「次々に修復」と当たり前にいっているが、どのようなメカニズムで修復されたと思っているのか。
なんでさっきから自然淘汰のこと無視するん?
自然淘汰ガン無視でござる。進化とは、じつは非常に場当たり的で、必ずしも(人間の価値観で)前に進んでいるだけとはいえないようだ。(p.87)
後者は賛成だが、そんな当たり前のことをなにドヤ顔で……。
この時点で読むのをやめてもよかったのだが、逆に面白くなってきたので続けよう。
なにを言ってるのかわからない……。これまでは、単細胞生物の細菌から多細胞生物までが同列に扱われてきたうえに、植物と動物も完全にごちゃまぜになって進化が考えられてきた。(中略)ダーウィンがおかした大きなまちがいも、彼が動物も植物もなにもかもごちゃまぜにして進化を論じた点である。このことは、科学的な方法として正しくないだけでなく、結果的に進化の本質を見落とすことにつながってしまった。(p.38-40)
地球上のすべての生物にはDNAという共通する要素がある。
植物だろうが動物だろうが地球外生命体だろうが適用できる普遍性こそがダーウィニズムだ。
特定の種類の動物、この著者が取り上げるのは脊椎動物だが、それだけの進化を論じても、じゃあそれ以外の生物はどう説明するの? という話になる。
もちろん本書はその点について黙して語らない。
くわしくは著者の具体的な実験と説を見て考えよう。
第2章ではサメについての実験が紹介されている。
サメを麻酔海水につけるとのたうち回って陸上に逃げるらしい。
のたうち回ると血圧が上がり、エラで空気呼吸ができるようになる。
何回も繰り返すと、最初は20分で息絶え絶えだったサメが、1時間陸上に放っても平気になる。
エラの一部が袋状になって肺になるのは時間の問題である。
ヒトも、はじめは1分息を止めるだけで苦しそうにするが、訓練次第で5分は止められるようになる。やがて息をしなくても生きられるようになるのは時間の問題である。
馬鹿な。
本気で正気を疑った。
いや、本文に書いてあるのはもちろんサメのくだりだけね。
他にも血流が多いと肝臓に埋め込んだ軟骨が硬骨になってしまうんだとか。
専門的なことはよくわからないけれど、要約すると訓練次第でサメが哺乳類的なものを獲得するんだと。
なるほど、それは興味深い実験ですね。
で、それが進化とどう関係するんで……?
おわかりいただけませんでした!本章の考察で、脊椎動物の進化にかぎって考えれば、それはダーウィン的「進化の総合説」によって突然変異と自然淘汰で説明されるものではなく、完全に重力を中心とする生体力学的な対応によって起こることをおわかり頂けたと思う。(p99)
で、次章にてようやく個体の変化が次の世代に伝わるメカニズムが語られるらしい。
重要なのはそこですから。混乱を避けるために触れなかった?
触れなかったせいで混乱しました!
いったいどんな読者を想定しているのやら。
第3章。
いったいどんなメカニズムが語れるのかな。ワクワク。
? ……?? ……!??
さっぱりわからん。
わからないなりに要点だけかいつまむと、「獲得形質の遺伝」についてはさすがの著者でも否定するらしい。
だが、「行動様式」が伝われば遺伝によらずとも獲得形質は次代に伝わる。
なるほど、つまりはミームというわけか。
子が親の行動を真似るというのは人間にかぎらず様々な動物でも観察できる。
つまりだ。あるサメがのたうち回って1時間陸上で生きられるようになった!
その子も親の真似をして1時間陸上で生きられるようになった!
さらにその子も親の真似をして1時間陸上で生きられるようになった!
さらにさらに(ry
で、いつになったらサメは陸上に進出できるんですかね?
「行動様式」が伝わってもそれは0からのスタートでしょ? 強くてニューゲームちゃいますやろ? 「次の世代」には伝わるかも知れないけど「次の次の世代」にはどう伝わるんです? 同じようにしか伝わりませんよね? 繰り返すうちに2時間陸生できるようにはなりませんよね? それとも僕がなにか読み違いしてるんですか?
……なにがなんだかわからない。
続けて「ワイスマン実験」批判。これもまるで意味がわからない。
ワイスマン実験とは、獲得形質の遺伝を否定したとされる有名な実験で、22代・1600匹のネズミの尾を切り続け、それが次代に遺伝しないことを証明した実験だ。
著者はこの実験を「二重の意味で愚か」であると批判している。
意味がわからないと思うが、僕もわからない。①ラマルクの「第二法則」は一般に「獲得形質の遺伝」とされているが、よく読めば必ずしも「遺伝」とはかぎらない。つまり、「行動様式」によって次代に伝わることもありうるのに、ワイスマンはその点を誤解している。
②ネズミにとって尾が切られることは獲得形質でもなんでもなく、ただの災難である。獲得していないものが次代に伝わるわけがない。
まず①だが、ラマルクについては僕も詳しくないのでなんともいえない。
だが、ワイスマンがラマルクを誤解していたからといって実験結果が変わるわけではない。
「獲得形質の遺伝の否定」、ワイスマン実験の意味はそれだ。
この点については、著者も「獲得形質が次代に遺伝することはあり得ない」(p.106)ハッキリ書いている。
ちなみに第3章のタイトルが『「遺伝」によらずとも変化は次代につながる』だ。
著者はなぜワイスマン実験を否定したかったのだろう。
著者の主張とワイスマン実験は別に矛盾しないはずだ。
実験は正しいがこんな実験に意味はない! とでもいいたいのだろうか?
そして②について。
サメにとっても麻酔海水に浸けられるのはただの災難でしかないだろうに。
なになに、サメは陸上にあがって1時間も無事でいられる形質を獲得した?
では、獲得形質と怪我をどう区別するのか。
わかりやすいようヒトの例で考えよう。
筋肉トレーニングとは、人為的に筋肉を痛めつける行為だ。
痛めつけられることで超回復が起こり、何度も繰り返すうちに筋肉が肥大化する。
これを「獲得形質」であると定義することには著者も納得してくれるだろう。
では、もう一例。事故によって指がごっそりもげた。
放っておくと、皮膚が傷口を覆うように再生し、指は短くなったが傷口はふさがった。
さて、筋トレと怪我の再生との差異はなにか。
怪我が起こり、それが回復した。どちらも同じことだ。
前者は結果的に肥大化し、後者は指が短くなった。
その違いはあるが、両者をどう区別するのか。
尻尾を切られたマウスでも同様のことが起こったはずだ。
傷を再生し、なんらかの形質を獲得したはずだ。
視点を変えよう。
サメはなぜ陸上でも1時間生きられる形質を獲得できたのか。
著者は「ウォルフの法則」を根拠に「当然」だとしている。
機能が変わると、形もその機能の変化にしたがって変化する。
いや、それこそ経験則ですやん。
ダーウィニズムを「論」にすぎず、「法則」にはほど遠いと批判しておきながら「ウォルフの法則」という経験則にすぎないものを支持するとはいやはや。
ダーウィニズム的に答えるならこうだ。
陸上に打ち上げられるような経験は滅多にないが、何度も起こるようならその環境にある程度適応できた方が生存に有利だったからだ。
筋肉トレーニングもそうだ。痛めつけるほど何度も使う部位なら、超回復により肥大化させた方がいい。その方が明らかに生存に有利だ。
これが突然変異と自然淘汰によって生まれたシステムだ。
まとめよう。
この著者はいったいなにが主張したいのか。
まず本書のタイトルにある「重力」。
本記事ではここまで無視してきたが、もちろん本書では重力と進化の関係について様々な例を書いている。
たとえば、重力によって個体の骨格や形が変化して「ほら、ホヤの幼生が魚っぽくなるでしょ?」というような例が紹介されていたりする。
サメの例も、水の中から陸上に上げられ見かけ上重力が6倍になったことへの適応だとしてしている。
が、そもそも獲得形質が遺伝しないことには進化とは関係しようがない。
よってこの記事では無視してきた。
進化とは無関係のレベルでしか「重力」は扱われていないからだ。
仮に重力が進化に関わるなら、重力はすべての生物に平等にかかる力であるため、生物の多様性が説明できない、という反論もできる。
また、著者がダーウィニズムを否定する論拠としては、①突然変異体はふつうすぐ死ぬ、②著者の貧弱な想像力では進化に関わるとは思えない、という二点である。
いずれもダーウィニズムを根本から誤解しているのと、自然淘汰のことをすっぽり忘れているにすぎない。
そして「我々は遺伝子を過大評価しすぎてきた」というようなことも書いている。
遺伝によらずとも、行動様式が伝わることで形質もまた次代に伝わることがある。
だが、次の次の世代にどのように伝わるのかについては本書は黙して語らない。
以上、非常にキチガイじみていて面白い本でした。
できるかぎり本書の狂気を伝えようと長々と書きましたが、これだけだとなにがなんだかわからないことでしょう。
そういう方は自らの手で本書を手に取ってみるのはいかがでしょうか。
きっとなにがなんだかわからないはずです。
生物は重力が進化させた (ブルーバックス)
こんなトンデモ本読んでられるか! 俺はまともな進化生物学へ帰る!
という方は、以下の本がオススメです。
利己的な遺伝子 <増補新装版>
盲目の時計職人
進化の存在証明
PR
まずはこの著者・泉和良の解説からしなければならない。
彼は「アンディーメンテ」というサークルにてジスカルド名義で大量のフリーゲームを制作している。
一発ネタのおふざけゲームも多いが、『アールエス』を代表に、『スペースクウィーン』『自給自足』『君が忘れていった水槽』『AIRAM EVA』などよく作り込まれた名作も多い。
ジャンルも、RPG、シューティング、アクション、ライフゲームなど様々だ。
ゲーム性やビジュアルについては人を選ぶかもしれないが、音楽は人を選ばないことに定評がある。
そして、彼の作品の魅力としてSFがある。
先に挙げた作品でもそうだし、SF作家としての彼が知りたいのならばノベルゲーム『きせきの扉』『全人類5万年ひきこもり』がオススメだ。
また、「イズミカズヨシ」名義で数作のSF短編も発表している。
『ヘルメスよ、ハデスに我の名を告げよ』
『塔の者』
『おやすみ、コネコ』
『日の光、血の光』
『星ぼしはオレの敵だ、星がわたしの夫なんです』
蛇足にはなるが、彼は他にも「ジェバンニP」という顔も持ち、ニコニコ動画にて複数の楽曲を発表している。
他にも別名義で「テレパスミュージック」という企画を主催していたり、突発的にネットラジオをしたりと、ともかく様々な顔を持つ彼だが、ついには小説家としてデビューする。
第一作目は『エレGY』。
半自伝的な恋愛小説で、主人公は作者そのもの、フリーゲーム作家としての彼を知ることができる。
ただし、彼女の存在は妄想である。
もとよりAMファンだった僕にはとても面白い小説だったが、知らない人にとってはどうなのかはわからないw
逆にまったく知らない人だと「え? これマジなの?」と思わずググらずにはいられない小説だろう。
第二作目は『spica』。
「恋愛は甘くて音楽のように心地の良いものだと思っているやつがいたら死ね」
虚実の織り交ぜられたテキスト、フィクションのなかのフィクションという二重構造が不確かな現実を確かなものにする。
そんな矛盾めいた表現、しかしそれ以外に、僕はこの作品の不思議な浮遊感を表現する術を持たない。
逃げよう逃げようと懸命になるほどに、逃げることの出来ない現実の重圧がのしかかる。
弱く、ちっぽけで、かといって安っぽい幻想に逃げ込むこともできない。
不安定なまま加速する物語が実に快い。
物語は終わりと共にはじまり、長い苦悩を経て物語はある程度は収束するも、それは新たなはじまりにすぎない。
関係は続く。
これもまた恋愛小説であり、話としては前作とたいして変わらない。
主人公は音楽作家としての作者が投影されている。ニートなのは相変わらず。
文章は洗練された感がある。
あまり恋愛小説自体読まないので相対的な評価はできないが、絶対的には面白かった。
「愛」についてよく考えられた小説である。
第三作目は『ヘドロ宇宙モデル』。
これは、はっきり言って駄作だ!
駄目人間。不思議少女。いつでもやれる女。
前作、前々作とまったく同じ構図。またそのパターンかよ!
本作では人間関係が単純化されすぎというか、作者の願望と妄想をダラダラ垂れ流した印象が強い。
主人公がなにかしらのクリエイターで、そのファンの女の子と仲良くなる。
そればっかり。これも前作、前々作と同様。
「どんだけその願望が強いんだよww」とニヤニヤすることはできるが。
『spica』では虚言癖があり思い通りにいかないヒロインが魅力的であり、「愛」について重大なテーマに踏み込んでいたが、本作ではなにがテーマになってるのかよくわからない。
あ、どうでもいいけど「宇宙モデル」ってディックの「世界球」のパk
「メンヘラ恋愛小説はもういいからSF書け!!」
これはなにも僕ばかりの声ではない。AMスレでも同様の声があった。
そして待ちに待ったSF小説がやってきた。
『セドナ、鎮まりてあれかし』ハヤカワJAにて刊行!
はてさて、その内容は……?
正直、あんまり好きなタイプの話じゃなかった(´・ω・`)
つまらないというほどではなく、そこそこ面白かったけど、ファン補正がないと読めたもんじゃない、かもしれない。
「鎮魂」だとか「英霊」だとか、そういう宗教的なワードは嫌いなのです。
もちろん、この作品はあくまでSFで、神秘主義に陥るほどひどくはなかったけど。
そして実際、複雑な機械というものはときとして予想しない挙動をすることがあるので、まあリアルではあるけど。
登場人物の思想に過ぎない、といっても、対立する思想が出てくるわけではないのでどうにもバランス感覚に欠ける。
戦争に負けた太陽圏のくだりが旧日本軍を彷彿させて仕方がなかったり、ちょっと右翼的な思想が入ってたり。
あとは、あいかわらず文章表現が冗長。
面白かった点としては。
この小説は一人称なのか三人称なのか。
同じことを気にする人がどの程度いるのかわからないが、僕は気にする。
そしてどちらかというと三人称の方が好きだ。
パラパラとめくる。地の文に「私」と見える。
残念、一人称か。
とは思ったが、特に迷うことなく買う。
読んでみる。
これはいったい?
この小説は一人称の形式を借りた三人称だった!
主人公は尾野碁呂、しかし彼は地の文にて三人称で呼ばれている。
「私」は別にいるが、その場にいるわけではない。
ちょっと混乱したが、どうやら「私」はどこからか傍観している立場にあるらしい。
三人称小説でも、誰かに視点が固定され、誰かの心情が地の文で書かれてたり、あるいはなにものかの感想のようなものが混ざったりする。
この小説はそれを「私」が担当している設定なのだ。
ただ、「私」は決して物語と無関係の傍観者ではない。
じゃあ誰なの? ってことだけど、まあ予想通りでしたね。
テラフォーミングされ、戦争の激戦区となり、荒廃した辺境の惑星セドナ。
駐留する人間は2人+アンドロイド1体のみ。
彼らはただかつての戦死者の遺骨収集に明け暮れる。
そして過酷な環境のセドナには、それにふさわしい奇妙な植物が独自に進化していた。
このシチュエーションだけなら嫌いじゃない。
ただ、遺骨集めにガチで意義を見いだしてるのがどうも。
このへんになにかしらのシニカルな政治的事情とかあればよかったんだけど。
「彼はこれが立派なことだと信じているようだけれど、実際は……」みたいな。
構図が少し単純すぎて深みがなかった。
未知の植物の設定解説はそれだけで面白い。
しかしこれも、新しい単語が出てくるたびに「○○とは~」ってやられるのはちょっとげんなり。
もっと解説の仕方にパターンが欲しかったところ。
SF設定も、大きな矛盾は感じられなかったが、だいぶブラックボックスに頼った、ありきたりで甘い設定になっている。いわゆる「ハードSF」には分類できないだろう。
僕の好きなSFにはだいたい2通りあり、
①レムやイーガンのように、現代科学理論を取り入れながら、説得力のある、複雑で体系立ったSF理論を展開するもの
②『BLAME!』のように、魅力的な世界観や造語を提示しながら、あえて詳細な説明を控え、読者の想像力を刺激するもの
AM作品は基本的に後者で、本作もまあ後者。
ただ、数々の造語にそこまでセンスがあったかというと……。
悪くはないけど、そこまでよくもないかな。
気になったのは、西暦3000年の未来医療でも尾野碁呂の脳障害は治療できないのか、といったあたり。
まあ、これも「できなかったのだろう」と解釈するほかあるまい。
以上、『セドナ、鎮まりてあれかし』はそこまで面白くはなかったけれど、『きせきの扉』はマジで面白い!
うーむ、じすさん、あんまり長編には向かないのかなあ。
彼は「アンディーメンテ」というサークルにてジスカルド名義で大量のフリーゲームを制作している。
一発ネタのおふざけゲームも多いが、『アールエス』を代表に、『スペースクウィーン』『自給自足』『君が忘れていった水槽』『AIRAM EVA』などよく作り込まれた名作も多い。
ジャンルも、RPG、シューティング、アクション、ライフゲームなど様々だ。
ゲーム性やビジュアルについては人を選ぶかもしれないが、音楽は人を選ばないことに定評がある。
そして、彼の作品の魅力としてSFがある。
先に挙げた作品でもそうだし、SF作家としての彼が知りたいのならばノベルゲーム『きせきの扉』『全人類5万年ひきこもり』がオススメだ。
また、「イズミカズヨシ」名義で数作のSF短編も発表している。
『ヘルメスよ、ハデスに我の名を告げよ』
『塔の者』
『おやすみ、コネコ』
『日の光、血の光』
『星ぼしはオレの敵だ、星がわたしの夫なんです』
蛇足にはなるが、彼は他にも「ジェバンニP」という顔も持ち、ニコニコ動画にて複数の楽曲を発表している。
他にも別名義で「テレパスミュージック」という企画を主催していたり、突発的にネットラジオをしたりと、ともかく様々な顔を持つ彼だが、ついには小説家としてデビューする。
第一作目は『エレGY』。
半自伝的な恋愛小説で、主人公は作者そのもの、フリーゲーム作家としての彼を知ることができる。
ただし、彼女の存在は妄想である。
もとよりAMファンだった僕にはとても面白い小説だったが、知らない人にとってはどうなのかはわからないw
逆にまったく知らない人だと「え? これマジなの?」と思わずググらずにはいられない小説だろう。
第二作目は『spica』。
「恋愛は甘くて音楽のように心地の良いものだと思っているやつがいたら死ね」
虚実の織り交ぜられたテキスト、フィクションのなかのフィクションという二重構造が不確かな現実を確かなものにする。
そんな矛盾めいた表現、しかしそれ以外に、僕はこの作品の不思議な浮遊感を表現する術を持たない。
逃げよう逃げようと懸命になるほどに、逃げることの出来ない現実の重圧がのしかかる。
弱く、ちっぽけで、かといって安っぽい幻想に逃げ込むこともできない。
不安定なまま加速する物語が実に快い。
物語は終わりと共にはじまり、長い苦悩を経て物語はある程度は収束するも、それは新たなはじまりにすぎない。
関係は続く。
これもまた恋愛小説であり、話としては前作とたいして変わらない。
主人公は音楽作家としての作者が投影されている。ニートなのは相変わらず。
文章は洗練された感がある。
あまり恋愛小説自体読まないので相対的な評価はできないが、絶対的には面白かった。
「愛」についてよく考えられた小説である。
第三作目は『ヘドロ宇宙モデル』。
これは、はっきり言って駄作だ!
駄目人間。不思議少女。いつでもやれる女。
前作、前々作とまったく同じ構図。またそのパターンかよ!
本作では人間関係が単純化されすぎというか、作者の願望と妄想をダラダラ垂れ流した印象が強い。
主人公がなにかしらのクリエイターで、そのファンの女の子と仲良くなる。
そればっかり。これも前作、前々作と同様。
「どんだけその願望が強いんだよww」とニヤニヤすることはできるが。
『spica』では虚言癖があり思い通りにいかないヒロインが魅力的であり、「愛」について重大なテーマに踏み込んでいたが、本作ではなにがテーマになってるのかよくわからない。
あ、どうでもいいけど「宇宙モデル」ってディックの「世界球」のパk
「メンヘラ恋愛小説はもういいからSF書け!!」
これはなにも僕ばかりの声ではない。AMスレでも同様の声があった。
そして待ちに待ったSF小説がやってきた。
『セドナ、鎮まりてあれかし』ハヤカワJAにて刊行!
はてさて、その内容は……?
正直、あんまり好きなタイプの話じゃなかった(´・ω・`)
つまらないというほどではなく、そこそこ面白かったけど、ファン補正がないと読めたもんじゃない、かもしれない。
「鎮魂」だとか「英霊」だとか、そういう宗教的なワードは嫌いなのです。
もちろん、この作品はあくまでSFで、神秘主義に陥るほどひどくはなかったけど。
そして実際、複雑な機械というものはときとして予想しない挙動をすることがあるので、まあリアルではあるけど。
登場人物の思想に過ぎない、といっても、対立する思想が出てくるわけではないのでどうにもバランス感覚に欠ける。
戦争に負けた太陽圏のくだりが旧日本軍を彷彿させて仕方がなかったり、ちょっと右翼的な思想が入ってたり。
あとは、あいかわらず文章表現が冗長。
面白かった点としては。
この小説は一人称なのか三人称なのか。
同じことを気にする人がどの程度いるのかわからないが、僕は気にする。
そしてどちらかというと三人称の方が好きだ。
パラパラとめくる。地の文に「私」と見える。
残念、一人称か。
とは思ったが、特に迷うことなく買う。
読んでみる。
これはいったい?
この小説は一人称の形式を借りた三人称だった!
主人公は尾野碁呂、しかし彼は地の文にて三人称で呼ばれている。
「私」は別にいるが、その場にいるわけではない。
ちょっと混乱したが、どうやら「私」はどこからか傍観している立場にあるらしい。
三人称小説でも、誰かに視点が固定され、誰かの心情が地の文で書かれてたり、あるいはなにものかの感想のようなものが混ざったりする。
この小説はそれを「私」が担当している設定なのだ。
ただ、「私」は決して物語と無関係の傍観者ではない。
じゃあ誰なの? ってことだけど、まあ予想通りでしたね。
テラフォーミングされ、戦争の激戦区となり、荒廃した辺境の惑星セドナ。
駐留する人間は2人+アンドロイド1体のみ。
彼らはただかつての戦死者の遺骨収集に明け暮れる。
そして過酷な環境のセドナには、それにふさわしい奇妙な植物が独自に進化していた。
このシチュエーションだけなら嫌いじゃない。
ただ、遺骨集めにガチで意義を見いだしてるのがどうも。
このへんになにかしらのシニカルな政治的事情とかあればよかったんだけど。
「彼はこれが立派なことだと信じているようだけれど、実際は……」みたいな。
構図が少し単純すぎて深みがなかった。
未知の植物の設定解説はそれだけで面白い。
しかしこれも、新しい単語が出てくるたびに「○○とは~」ってやられるのはちょっとげんなり。
もっと解説の仕方にパターンが欲しかったところ。
SF設定も、大きな矛盾は感じられなかったが、だいぶブラックボックスに頼った、ありきたりで甘い設定になっている。いわゆる「ハードSF」には分類できないだろう。
僕の好きなSFにはだいたい2通りあり、
①レムやイーガンのように、現代科学理論を取り入れながら、説得力のある、複雑で体系立ったSF理論を展開するもの
②『BLAME!』のように、魅力的な世界観や造語を提示しながら、あえて詳細な説明を控え、読者の想像力を刺激するもの
AM作品は基本的に後者で、本作もまあ後者。
ただ、数々の造語にそこまでセンスがあったかというと……。
悪くはないけど、そこまでよくもないかな。
気になったのは、西暦3000年の未来医療でも尾野碁呂の脳障害は治療できないのか、といったあたり。
まあ、これも「できなかったのだろう」と解釈するほかあるまい。
以上、『セドナ、鎮まりてあれかし』はそこまで面白くはなかったけれど、『きせきの扉』はマジで面白い!
うーむ、じすさん、あんまり長編には向かないのかなあ。
( ・3・)クリスマスだよ~。
当日うpなのに謎の出遅れた感!
季節感ガン無視のサンタ娘をうpりました。
そういえば、一年くらい前につくったノベルゲーム『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』もクリスマスが題材の作品でしたね。
ぶっちゃけクリスマスほとんど関係ないけど。
クリスマスに間に合わせることを目標にクリスマスを題材にしてたのに間に合わなくて、一年遅れても間に合わなくて、結局2月くらいに発表したと思います。
「絶対悪」とはなにか、という議論。
たとえばドラゴンボールのフリーザ。
トランクスに瞬殺されたメカフリーザの存在は無視し、フリーザという巨大な「悪」にかかる問題を、物語としていかに解決しえたか。
法倫理的・法正義的な観点からいえば、悟空がフリーザを逮捕あるいは説得、警察に引き渡し、然るべき裁判を受け、罪刑法定主義に基づき正当な裁きを下す。
そういったシナリオが本来ならば「あるべき」結末だ。
しかし、それが失笑に値するほどの不可能であることはいちいちいうまでもない。
いかなる警察勢力もフリーザを拘束することはできないし、フリーザが改心ないし更正するなどということはとても考えられないからだ。
悟空がスーパーサイヤ人として覚醒し、圧倒的な実力差が生じたあとですら、フリーザは「悪」であることを心底諦めなかった。
悟空は何度も彼を許そうとしたにもかかわらず、フリーザはそれを認めなかった。
だから悟空はフリーザを「殺すしかなかった」。
「殺すしかなかった」――絶対悪とはそれだ。
フリーザを殺すことによって物語はひとまず収束する(フリーザ編は終了する)が、それは決してハッピーエンドではない。
「殺すしかない」ということ。それは悲劇だ。
いかにフリーザが極悪非道の存在でも、ただの人間であれば法に基づいた正当な手続きによって裁きを下すことは(物理的には)可能だ。
巨大な組織を解体し、すべての屈強な部下から隔離し、資本金も根こそぎ奪ったなら、どんな極悪人でも大人しく法廷に立たざるを得ない。
それが不可能であるのは、フリーザが一個人で宇宙最強の暴力を保有していたからに他ならない。
誰がどう見ても破落戸の某国を通常の刑法犯のように裁けないのも同じ理由だ。
「悪」が「絶対」であるためにはいかなる拘束を受け付けないだけの暴力が必要条件になる。
だが、「悪」が個人であるかぎり、現実的に考えて手錠をかけられた時点で抵抗はできない。
個人が絶対悪たり得ないのはそのためだ。
さて、以上を踏まえてネウロの「シックス」の話。
彼は「絶対悪」として登場し、そしてそう呼ばれるにふさわしい最期を迎えた。
「殺すしかなかった」――だが、本当にそうだったのだろうか?
たしかに、シックスはその組織力もさることながら、一個人で(弱体化した)ネウロと渡り合うほどの暴力を保有している。
また、胴体が真っ二つになっても生存できるという驚異的な生命力も有している。
だが、彼はあくまで「人間」、ないしその延長上の存在にすぎない。
フリーザほど「警察などではどうにもならない」という説得力に欠けるのだ。
特に、超人的な主人公や悪役のなか、この作品は他の少年漫画に比べ警察がよく活躍する。
もしかしたら彼らなら、シックスを逮捕し、正当な手続きで裁きを下すことも可能だったのではないか?――そう思えるほどに。
しかし、結果としてシックスと警察が真っ向からぶつかり合うことはなかった。
個人的にはそういった展開が見たかったが、もしシックスを絶対悪として強調するなら、警察ではいかなる手段を用いても手も足も出ないということを明確に描写すべきだった(それでもなお、最終的には警察がシックスを逮捕するという展開を望むが)。
結末は、他の少年漫画と同じく主人公が半ば独善的にシックスを殺害するという形となる。
最終的には圧倒的な力の差が生じ、主人公の裁量如何によって殺すか否かという選択を迫られたという点でフリーザとシックスは共通する。
すなわち相手はボロボロに追い詰められ、抵抗する力をほとんど殺がれ、主人公が引き金をひけばすぐにでも殺せる状況だ。
だが、悟空がフリーザを許そうとしたのに対し、ネウロはシックスを端から殺すつもりでいて、最後まで許さなかった。
この点で両者は大きく異なる。
たしかにキャラクターの性格として、悟空は情に脆かったりどこか甘いところがあり、ネウロはそもそも人間でないなどの違いはある。
だが、「シックスを許そうとする」立場として弥子がそこに立てたはずだ。
弥子はシックスに親しい人間を殺されてはいるが、それをいうなら悟空も同じだ(ドラゴンボールで生き返らせられるという違いはあるが)。
シックスを許そうという発想はフリーザを許そうとするのと同じくらい馬鹿げてはいるが、しかしそれでも、それを試みるチャンスもなく、ましてや発想も浮かばないというのは、やはり哀しい。
特に弥子がそこに立てなかったのはとても哀しい。
その意味で、そんな発想すら浮かばないという意味で、シックスは作中では「絶対悪」としての地位を確立しているかもしれないが、しかし、どうにも作者の都合で強引に「絶対悪」に仕立て上げられたのだという印象が消えないのだ。
フリーザが、許そうとしてもなお許すわけにはいかない存在であったのに対し、シックスははじめから絶対悪として設定され、はじめから許すつもりなどない存在として描かれた。
結果として、皮肉なことに「絶対悪」としての説得力に欠けてしまう。
「殺すしかなかった」という意味で異常な説得力を帯びる悪役としては、他には『ヘルシング』の少佐が印象深い。
彼はあくまで「人間」であり、物理的には逮捕・拘留……といった手順を踏むことは可能だった。
ただ、彼はその罪状があまりにも大きすぎる(被害者約380万という狂気)し、なにより手に負えないほど「狂って」いた。
彼が更正するなど天地がひっくり返ってもあり得ないし、仮に逮捕し裁判にかけても死刑以外にあり得ないだろう。
仮に死刑廃止国であったとしても、世論が彼の生存を許すだろうか?
そんな冷静な議論ができるほど高い民度を備えた国家はこの地上に存在しない。
そもそも彼は一度完膚無きまでに敗れたはずなのだ。
にもかかわらず50年の月日を経て蘇り、空前絶後の大犯罪をなした。
そして、もし彼をまた逃すようなことがあれば、50年後にさらなる悲劇が繰り返されるだろう。
「未来を裁くことはできない」――しかし、彼なら間違いなくそうするという強烈な説得力がある。
つまり彼は心理的な意味で「絶対悪」なのだ。
あの状況下に立ってしまえば、インテグラだろうが誰だろうが、彼を「撃ち殺す」以外にはない。
彼を逮捕し拘留し……などという選択肢が頭をよぎることは(仮に可能であっても)ない。
少佐としては、その場で殺されることより、逮捕され刑務所送りのなる方が、よほど屈辱であったに違いないのに。
しかし、あくまでそれは心理的なものだ。
物理法則には抗えなくとも、心理的な拘束なら自由意志によってどうとでもなるはずだ。
それができない。自由意志は否定された。
彼を「殺した」のか、それとも「殺すしかなかった」のか。それは結果的には同じでも大きな違いだ。
ほとんどの作品はその悲劇から積極的に目を背ける(『ヘルシング』も『ネウロ』も然り)。
目を背けなければ「いられない」のだ。
なんという悲劇だろうか。
「絶対悪などあり得ない」その観点に立ち、はじめて我々は絶対悪とはなにかを知る。
それは正義の弱さなのだ。
絶対悪を許さないこと、すなわち「殺すしかない」と断ずること。
逆説的に、それこそが絶対悪の存在を「許して」いるというわけだ。
たとえばドラゴンボールのフリーザ。
トランクスに瞬殺されたメカフリーザの存在は無視し、フリーザという巨大な「悪」にかかる問題を、物語としていかに解決しえたか。
法倫理的・法正義的な観点からいえば、悟空がフリーザを逮捕あるいは説得、警察に引き渡し、然るべき裁判を受け、罪刑法定主義に基づき正当な裁きを下す。
そういったシナリオが本来ならば「あるべき」結末だ。
しかし、それが失笑に値するほどの不可能であることはいちいちいうまでもない。
いかなる警察勢力もフリーザを拘束することはできないし、フリーザが改心ないし更正するなどということはとても考えられないからだ。
悟空がスーパーサイヤ人として覚醒し、圧倒的な実力差が生じたあとですら、フリーザは「悪」であることを心底諦めなかった。
悟空は何度も彼を許そうとしたにもかかわらず、フリーザはそれを認めなかった。
だから悟空はフリーザを「殺すしかなかった」。
「殺すしかなかった」――絶対悪とはそれだ。
フリーザを殺すことによって物語はひとまず収束する(フリーザ編は終了する)が、それは決してハッピーエンドではない。
「殺すしかない」ということ。それは悲劇だ。
いかにフリーザが極悪非道の存在でも、ただの人間であれば法に基づいた正当な手続きによって裁きを下すことは(物理的には)可能だ。
巨大な組織を解体し、すべての屈強な部下から隔離し、資本金も根こそぎ奪ったなら、どんな極悪人でも大人しく法廷に立たざるを得ない。
それが不可能であるのは、フリーザが一個人で宇宙最強の暴力を保有していたからに他ならない。
誰がどう見ても破落戸の某国を通常の刑法犯のように裁けないのも同じ理由だ。
「悪」が「絶対」であるためにはいかなる拘束を受け付けないだけの暴力が必要条件になる。
だが、「悪」が個人であるかぎり、現実的に考えて手錠をかけられた時点で抵抗はできない。
個人が絶対悪たり得ないのはそのためだ。
さて、以上を踏まえてネウロの「シックス」の話。
彼は「絶対悪」として登場し、そしてそう呼ばれるにふさわしい最期を迎えた。
「殺すしかなかった」――だが、本当にそうだったのだろうか?
たしかに、シックスはその組織力もさることながら、一個人で(弱体化した)ネウロと渡り合うほどの暴力を保有している。
また、胴体が真っ二つになっても生存できるという驚異的な生命力も有している。
だが、彼はあくまで「人間」、ないしその延長上の存在にすぎない。
フリーザほど「警察などではどうにもならない」という説得力に欠けるのだ。
特に、超人的な主人公や悪役のなか、この作品は他の少年漫画に比べ警察がよく活躍する。
もしかしたら彼らなら、シックスを逮捕し、正当な手続きで裁きを下すことも可能だったのではないか?――そう思えるほどに。
しかし、結果としてシックスと警察が真っ向からぶつかり合うことはなかった。
個人的にはそういった展開が見たかったが、もしシックスを絶対悪として強調するなら、警察ではいかなる手段を用いても手も足も出ないということを明確に描写すべきだった(それでもなお、最終的には警察がシックスを逮捕するという展開を望むが)。
結末は、他の少年漫画と同じく主人公が半ば独善的にシックスを殺害するという形となる。
最終的には圧倒的な力の差が生じ、主人公の裁量如何によって殺すか否かという選択を迫られたという点でフリーザとシックスは共通する。
すなわち相手はボロボロに追い詰められ、抵抗する力をほとんど殺がれ、主人公が引き金をひけばすぐにでも殺せる状況だ。
だが、悟空がフリーザを許そうとしたのに対し、ネウロはシックスを端から殺すつもりでいて、最後まで許さなかった。
この点で両者は大きく異なる。
たしかにキャラクターの性格として、悟空は情に脆かったりどこか甘いところがあり、ネウロはそもそも人間でないなどの違いはある。
だが、「シックスを許そうとする」立場として弥子がそこに立てたはずだ。
弥子はシックスに親しい人間を殺されてはいるが、それをいうなら悟空も同じだ(ドラゴンボールで生き返らせられるという違いはあるが)。
シックスを許そうという発想はフリーザを許そうとするのと同じくらい馬鹿げてはいるが、しかしそれでも、それを試みるチャンスもなく、ましてや発想も浮かばないというのは、やはり哀しい。
特に弥子がそこに立てなかったのはとても哀しい。
その意味で、そんな発想すら浮かばないという意味で、シックスは作中では「絶対悪」としての地位を確立しているかもしれないが、しかし、どうにも作者の都合で強引に「絶対悪」に仕立て上げられたのだという印象が消えないのだ。
フリーザが、許そうとしてもなお許すわけにはいかない存在であったのに対し、シックスははじめから絶対悪として設定され、はじめから許すつもりなどない存在として描かれた。
結果として、皮肉なことに「絶対悪」としての説得力に欠けてしまう。
「殺すしかなかった」という意味で異常な説得力を帯びる悪役としては、他には『ヘルシング』の少佐が印象深い。
彼はあくまで「人間」であり、物理的には逮捕・拘留……といった手順を踏むことは可能だった。
ただ、彼はその罪状があまりにも大きすぎる(被害者約380万という狂気)し、なにより手に負えないほど「狂って」いた。
彼が更正するなど天地がひっくり返ってもあり得ないし、仮に逮捕し裁判にかけても死刑以外にあり得ないだろう。
仮に死刑廃止国であったとしても、世論が彼の生存を許すだろうか?
そんな冷静な議論ができるほど高い民度を備えた国家はこの地上に存在しない。
そもそも彼は一度完膚無きまでに敗れたはずなのだ。
にもかかわらず50年の月日を経て蘇り、空前絶後の大犯罪をなした。
そして、もし彼をまた逃すようなことがあれば、50年後にさらなる悲劇が繰り返されるだろう。
「未来を裁くことはできない」――しかし、彼なら間違いなくそうするという強烈な説得力がある。
つまり彼は心理的な意味で「絶対悪」なのだ。
あの状況下に立ってしまえば、インテグラだろうが誰だろうが、彼を「撃ち殺す」以外にはない。
彼を逮捕し拘留し……などという選択肢が頭をよぎることは(仮に可能であっても)ない。
少佐としては、その場で殺されることより、逮捕され刑務所送りのなる方が、よほど屈辱であったに違いないのに。
しかし、あくまでそれは心理的なものだ。
物理法則には抗えなくとも、心理的な拘束なら自由意志によってどうとでもなるはずだ。
それができない。自由意志は否定された。
彼を「殺した」のか、それとも「殺すしかなかった」のか。それは結果的には同じでも大きな違いだ。
ほとんどの作品はその悲劇から積極的に目を背ける(『ヘルシング』も『ネウロ』も然り)。
目を背けなければ「いられない」のだ。
なんという悲劇だろうか。
「絶対悪などあり得ない」その観点に立ち、はじめて我々は絶対悪とはなにかを知る。
それは正義の弱さなのだ。
絶対悪を許さないこと、すなわち「殺すしかない」と断ずること。
逆説的に、それこそが絶対悪の存在を「許して」いるというわけだ。
プロフィール
@aebafuti からのツイート
公開中のゲーム作品
『ロリ巨乳の里にて』
パイズリセックスRPG。
『幽獄の14日間』
リソース管理型脱出RPG。
『カリスは影差す迷宮で』
仲間を弱らせて殺す遺跡探索RPG。
『黒先輩と黒屋敷の闇に迷わない』
探索ホラー風セクハラゲーム。
『英雄候補者たち』
特に変哲のない短編RPG。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
メタメタフィクションノベルゲーム。
『或る魔王軍の遍歴』
「主人公補正」によって哀れにも敗れていくすべての悪役に捧ぐ。
『ドアによる未来』
「どこでもドア」はいかに世界に影響を及ぼし、人類になにをもたらすのか。



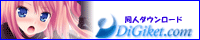
パイズリセックスRPG。
『幽獄の14日間』
リソース管理型脱出RPG。
『カリスは影差す迷宮で』
仲間を弱らせて殺す遺跡探索RPG。
『黒先輩と黒屋敷の闇に迷わない』
探索ホラー風セクハラゲーム。
『英雄候補者たち』
特に変哲のない短編RPG。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
メタメタフィクションノベルゲーム。
公開中の小説作品
「主人公補正」によって哀れにも敗れていくすべての悪役に捧ぐ。
『ドアによる未来』
「どこでもドア」はいかに世界に影響を及ぼし、人類になにをもたらすのか。


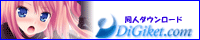
新着記事
2021 - 10 - 24
2020 - 12 - 03
2020 - 10 - 03
2020 - 06 - 30
2020 - 04 - 29
カテゴリー
アーカイブ
検索
新着コメント
[02 / 26 by 白蛇]
[02 / 26 by 白蛇]
[05 / 21 by 西 亮二]
[12 / 15 by NONAME]
[07 / 04 by アーミー]
ブックマーク
連絡先
aebafuti★yahoo.co.jp(★を@に変えて送ってください)
カウンター

