あえばさんのブログです。(※ブログタイトルはよろぱさんからいただきました)
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ソウヤーは『イリガール・エイリアン』でめっちゃ感動して『スタープレックス』で「あー、こんなもんか」ってなって、本作は「まあよくできてるんじゃない?」という印象。
ずば抜けて面白いわけではないけど、安定感のある外れのない作家なんじゃないかと思う。
いや、『イリガール・エイリアン』はめっちゃ面白いけど。名作だけど。
『スタープレックス』はスケールのわりに想像力が貧困なのよね。
驚くようなアイデアもあるにはあるけど。
閑話休題。
本作は、SFミステリというより解説にもあるように最新の科学知識を取り入れたミステリって感じで、SF要素は少ない。
僕としてはSF目当てで手に取ったのでちょっと残念ではあった。
ミステリにはあんまり興味ないし。
でも、保険会社の汚いやり方とか興味深いネタはちらほら。
「ハンチントン病」についても本作ではじめて知ったが、やばい病気もあるものだ。
優性遺伝性の不治致死病とかどんだけやねんと思ったけど、発症が35歳~50歳だから気づかずセックスして50%の確率で子に伝わり淘汰を免れる仕組みらしい。
SF要素はあんまない、といっても分子生物学とか遺伝学あたりはあんま詳しくないから単純に知識として新鮮だった。
というわけで、個人的には読む価値はあった。
ミステリとして評価するなら、あまりミステリを読んでいない僕からしてもそこまで斬新なネタやトリックがあるわけでもないように思えた。
読んでるうちはそれなりにハラハラドキドキするけどね。
出来はいいけど「ミステリ好きならこれは読め!」ってほどでもないかな。
ナチを出したのは遺伝子差別ネタで悪役ならナチだろっていう単純な連想なのかしら。
悪役の思考や所業が極端すぎる気がした。
「差別のない社会を!」みたいなオチにはなるけど「ナチはマジキチ」という偏見を前提にしてるのはどうなの。
ずば抜けて面白いわけではないけど、安定感のある外れのない作家なんじゃないかと思う。
いや、『イリガール・エイリアン』はめっちゃ面白いけど。名作だけど。
『スタープレックス』はスケールのわりに想像力が貧困なのよね。
驚くようなアイデアもあるにはあるけど。
閑話休題。
本作は、SFミステリというより解説にもあるように最新の科学知識を取り入れたミステリって感じで、SF要素は少ない。
僕としてはSF目当てで手に取ったのでちょっと残念ではあった。
ミステリにはあんまり興味ないし。
でも、保険会社の汚いやり方とか興味深いネタはちらほら。
「ハンチントン病」についても本作ではじめて知ったが、やばい病気もあるものだ。
優性遺伝性の不治致死病とかどんだけやねんと思ったけど、発症が35歳~50歳だから気づかずセックスして50%の確率で子に伝わり淘汰を免れる仕組みらしい。
SF要素はあんまない、といっても分子生物学とか遺伝学あたりはあんま詳しくないから単純に知識として新鮮だった。
というわけで、個人的には読む価値はあった。
ミステリとして評価するなら、あまりミステリを読んでいない僕からしてもそこまで斬新なネタやトリックがあるわけでもないように思えた。
読んでるうちはそれなりにハラハラドキドキするけどね。
出来はいいけど「ミステリ好きならこれは読め!」ってほどでもないかな。
ナチを出したのは遺伝子差別ネタで悪役ならナチだろっていう単純な連想なのかしら。
悪役の思考や所業が極端すぎる気がした。
「差別のない社会を!」みたいなオチにはなるけど「ナチはマジキチ」という偏見を前提にしてるのはどうなの。
PR
あらすじ:地球上に宇宙人飛来。
ファーストコンタクトは順調に進んでいたが、殺人事件が発生してしまい、その容疑者として宇宙人の一人が逮捕される。
そして前代未聞の裁判が始まる!
いやあ、このあらすじだけでもわくわくしちゃうね!
ジャンルはSFミステリとでもいえばいいか。
宇宙人を裁判にかけるという奇抜な状況設定。
その中で浮き彫りにされる司法の現実と理想。錯綜する思惑。
それだけでなく宇宙人の故郷、思想、生態などのSF的な考証も非常に興味深い。
様々な証拠、様々な解釈、様々な推測が重なり合い、たった一つの真実に辿り着く。
そして痛快なオチ!
この作品は全身全霊でオススメしたい。
ただ一つ惜しむらくは、宇宙人が人間的すぎるところか。
このテーマは『ソラリス』に譲ろう。
ファーストコンタクトは順調に進んでいたが、殺人事件が発生してしまい、その容疑者として宇宙人の一人が逮捕される。
そして前代未聞の裁判が始まる!
いやあ、このあらすじだけでもわくわくしちゃうね!
ジャンルはSFミステリとでもいえばいいか。
宇宙人を裁判にかけるという奇抜な状況設定。
その中で浮き彫りにされる司法の現実と理想。錯綜する思惑。
それだけでなく宇宙人の故郷、思想、生態などのSF的な考証も非常に興味深い。
様々な証拠、様々な解釈、様々な推測が重なり合い、たった一つの真実に辿り着く。
そして痛快なオチ!
この作品は全身全霊でオススメしたい。
ただ一つ惜しむらくは、宇宙人が人間的すぎるところか。
このテーマは『ソラリス』に譲ろう。
現在、僕が完成させた長・中編作品は5つ。
うち、公開している作品は3つです。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
『魔法少女シヌナ』
『Super Apple』
残り2作は、またなんらかの機会で。
タイトルは『malice』と『或る魔王軍の遍歴』というのですが。
普通にweb小説なんて公開しても読まれるわけねー! というのは分かり切っているので。
とまあ、これまで作品を書いてきたなかでいろいろ注意したり考えてきたことがあったわけですよ。
そのへん少しまとめてみたいと思います。
作品によってテーマは異なってくるが、共通するテーマもあります。
つまりは「社会の多様性」「人間の多面性」みたいなもの。
様々な立場にいる人間の思惑や利害が複雑に絡み合うような群像劇が好きなんです。
(それに外れているのが『メリクリ』と『超林檎』。この二作は一人称で登場人物の少ない話で、よくモチベーションが保ったものだと今となっては感心します)
それぞれ異なる文化環境に育ち、異なる思想を抱き、本来は関わり合うことなどないような両者があるきっかけのために出会い、対立する。
たとえばそういうシチュエーションが書きたいわけです。
『バキ』でいえば、空手の最強を信じひたすら鍛錬を続けてきた男と、訓練を女々しいと断じ拒否してきた男というまったく相反する思想のぶつかり合いなんて素敵ですよね。
しかし、内面が一切理解もできず想像もできないような人物はキャラクターとして登場させることは難い。
キャラが作者の分身以上の存在になり得ないなら作者自身の器を拡大するほかない。
となると、思想面においてはキャラは常に「劣化作者」にならざるをえない問題が生じる。
難しいですね。
この点は「作者の理想像」とか巧く使って。あとは実在の人物をモデルにするとか。
『魔法少女シヌナ』においてもこのへんはだいぶ意識しました。
たとえば、登場人物の一人である「ヴァルグ・ヴィロック」は「ヴァーグ・ヴァイカーネス」というあからさまなモデルがいます。
ヴィジュアルイメージもかなり似てます。訴えらえたりしないかしら。
ノルウェー出身であること。ワンマンバンドであること。教会への放火や、ライバルを殺害したこと。
このあたりのエピソードはまんまです。
とはいえ、もちろんなにからなにまで同じではありません。
思想面に関しては「作者の理想像」をうまく交えつつ、だいぶアレンジしてあります。
(「理想像=そうありたいと願う姿」じゃないからね! 注意!)
(あとは未公開作品である『malice』の主人公と設定がかなり被ってますが、それはまた別の話)
一方、この作品にはそんな彼とは一切無関係な分野のキャラも登場します。
中国黒社会です。なにを思って中国黒社会なんて登場させようと思ったのか。
というより、そもそもこの作品は「魔法少女」が主軸になる話。
そこに、普通だったらまるで関わりのないような、かつ明確なバックボーンのあるキャラクターを登場させ、絡ませる。
『魔法少女シヌナ』のコンセプトは大体そんな感じです。
さて、そのようなキャラクター中心の話になるなら魅力的なキャラクターを書くこと、キャラ立てが重要になってきます。
その方法として、キャラクターを立てるときは、そのキャラが死ぬことを前提に考えます。
もちろん全キャラを皆殺しにするつもりはありませんが、「もし死んだら……」と考えるわけです。
そのキャラが死んだときにどれだけ読者にショックを与えられるか。
与えられるならそのキャラは立っていた、といえる。
という風に。
殺すつもりでなければキャラ立てなんてやる気出ませんからね。
特に萌えキャラなんて、殺す以外に何の使い道があるのか。
つまり逆にいえば、どんなキャラなら死んだときにショックを受けるのか。
雑魚キャラや、はじめから死ぬのがわかっているようなあからさまな噛ませキャラの死は、もちろんショックを与えられません。
ならば、死ぬとは思われないようなキャラが死ねばショックも大きいでしょう。
『魔人探偵ネウロ』はこの点よくできてました。この作品におけるキャラの死には、ガチでショックを受けたものです。
さて、「その死にショックを受けるキャラ」とは、具体的にはどのようなキャラか。
たとえば、レギュラーキャラはもちろんそうです。
とはいえ、あからさまな死亡フラグが立っていたり、役割を終えてしまったようなキャラクターの予定調和な死にはなにも感じませんね。
どれだけ多くの物語を背負っているか。つまりは他のキャラクターとの関わりが指標になります。
愛すべき家族がいるから死ねない。ある目的を成し遂げるという役割が残っているから死ねない。
つまりは、そのキャラクターが死ぬことによってどれだけの物語が失われてしまうかということ。
死ぬという役割しかないようなキャラは、使い古された言い方をすれば、「殺す価値もない」わけですよ。
さて、そんな殺したがりの作者の描く物語の中で、登場人物が生き残るための方法は一つ。
「あれ? こいつ、生きてた方が面白くなるんじゃないか?」と作者に思わせること。
「あーあ、こいつ死んだな……」と思っていたキャラクターが生き残るときも、別のベクトルで驚きがあります。
死亡フラグが立ちまくっていたのに生き残るとそれはそれでカタルシスですよね。
たとえば、「実力未知数の敵キャラVS一度負けた敵キャラ」というマッチメイクがあれば、間違いなく前者が勝ちます。
ここでその法則を裏切って後者が勝つと熱いものがありますよね。
あるいは、死んでしまうと物語が急激につまらなくなってしまうような場合。
仮に『スタートレックTNG』でピカード艦長が作中で死亡すればそれはそれは大変なショックでしょうが、今後の物語に明らかな支障を来します。視聴者は間違いなく離れていくでしょう。
こんな感じで、殺すつもりで書いていたキャラが、殺すに殺せなくなり、結果生き残ってしまうわけです。
ジレンマですね。
でも萌えキャラを殺すときにはあまり躊躇を感じたことはないです。
あいつら死んだ方が絶対面白い。
うわああ萌えキャラを大量に登場させてズッコンバッコン殺しまくる話が書きたいよおおお!!
うち、公開している作品は3つです。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
『魔法少女シヌナ』
『Super Apple』
残り2作は、またなんらかの機会で。
タイトルは『malice』と『或る魔王軍の遍歴』というのですが。
普通にweb小説なんて公開しても読まれるわけねー! というのは分かり切っているので。
とまあ、これまで作品を書いてきたなかでいろいろ注意したり考えてきたことがあったわけですよ。
そのへん少しまとめてみたいと思います。
作品によってテーマは異なってくるが、共通するテーマもあります。
つまりは「社会の多様性」「人間の多面性」みたいなもの。
様々な立場にいる人間の思惑や利害が複雑に絡み合うような群像劇が好きなんです。
(それに外れているのが『メリクリ』と『超林檎』。この二作は一人称で登場人物の少ない話で、よくモチベーションが保ったものだと今となっては感心します)
それぞれ異なる文化環境に育ち、異なる思想を抱き、本来は関わり合うことなどないような両者があるきっかけのために出会い、対立する。
たとえばそういうシチュエーションが書きたいわけです。
『バキ』でいえば、空手の最強を信じひたすら鍛錬を続けてきた男と、訓練を女々しいと断じ拒否してきた男というまったく相反する思想のぶつかり合いなんて素敵ですよね。
しかし、内面が一切理解もできず想像もできないような人物はキャラクターとして登場させることは難い。
キャラが作者の分身以上の存在になり得ないなら作者自身の器を拡大するほかない。
となると、思想面においてはキャラは常に「劣化作者」にならざるをえない問題が生じる。
難しいですね。
この点は「作者の理想像」とか巧く使って。あとは実在の人物をモデルにするとか。
『魔法少女シヌナ』においてもこのへんはだいぶ意識しました。
たとえば、登場人物の一人である「ヴァルグ・ヴィロック」は「ヴァーグ・ヴァイカーネス」というあからさまなモデルがいます。
ヴィジュアルイメージもかなり似てます。訴えらえたりしないかしら。
ノルウェー出身であること。ワンマンバンドであること。教会への放火や、ライバルを殺害したこと。
このあたりのエピソードはまんまです。
とはいえ、もちろんなにからなにまで同じではありません。
思想面に関しては「作者の理想像」をうまく交えつつ、だいぶアレンジしてあります。
(「理想像=そうありたいと願う姿」じゃないからね! 注意!)
(あとは未公開作品である『malice』の主人公と設定がかなり被ってますが、それはまた別の話)
一方、この作品にはそんな彼とは一切無関係な分野のキャラも登場します。
中国黒社会です。なにを思って中国黒社会なんて登場させようと思ったのか。
というより、そもそもこの作品は「魔法少女」が主軸になる話。
そこに、普通だったらまるで関わりのないような、かつ明確なバックボーンのあるキャラクターを登場させ、絡ませる。
『魔法少女シヌナ』のコンセプトは大体そんな感じです。
さて、そのようなキャラクター中心の話になるなら魅力的なキャラクターを書くこと、キャラ立てが重要になってきます。
その方法として、キャラクターを立てるときは、そのキャラが死ぬことを前提に考えます。
もちろん全キャラを皆殺しにするつもりはありませんが、「もし死んだら……」と考えるわけです。
そのキャラが死んだときにどれだけ読者にショックを与えられるか。
与えられるならそのキャラは立っていた、といえる。
という風に。
殺すつもりでなければキャラ立てなんてやる気出ませんからね。
特に萌えキャラなんて、殺す以外に何の使い道があるのか。
つまり逆にいえば、どんなキャラなら死んだときにショックを受けるのか。
雑魚キャラや、はじめから死ぬのがわかっているようなあからさまな噛ませキャラの死は、もちろんショックを与えられません。
ならば、死ぬとは思われないようなキャラが死ねばショックも大きいでしょう。
『魔人探偵ネウロ』はこの点よくできてました。この作品におけるキャラの死には、ガチでショックを受けたものです。
さて、「その死にショックを受けるキャラ」とは、具体的にはどのようなキャラか。
たとえば、レギュラーキャラはもちろんそうです。
とはいえ、あからさまな死亡フラグが立っていたり、役割を終えてしまったようなキャラクターの予定調和な死にはなにも感じませんね。
どれだけ多くの物語を背負っているか。つまりは他のキャラクターとの関わりが指標になります。
愛すべき家族がいるから死ねない。ある目的を成し遂げるという役割が残っているから死ねない。
つまりは、そのキャラクターが死ぬことによってどれだけの物語が失われてしまうかということ。
死ぬという役割しかないようなキャラは、使い古された言い方をすれば、「殺す価値もない」わけですよ。
さて、そんな殺したがりの作者の描く物語の中で、登場人物が生き残るための方法は一つ。
「あれ? こいつ、生きてた方が面白くなるんじゃないか?」と作者に思わせること。
「あーあ、こいつ死んだな……」と思っていたキャラクターが生き残るときも、別のベクトルで驚きがあります。
死亡フラグが立ちまくっていたのに生き残るとそれはそれでカタルシスですよね。
たとえば、「実力未知数の敵キャラVS一度負けた敵キャラ」というマッチメイクがあれば、間違いなく前者が勝ちます。
ここでその法則を裏切って後者が勝つと熱いものがありますよね。
あるいは、死んでしまうと物語が急激につまらなくなってしまうような場合。
仮に『スタートレックTNG』でピカード艦長が作中で死亡すればそれはそれは大変なショックでしょうが、今後の物語に明らかな支障を来します。視聴者は間違いなく離れていくでしょう。
こんな感じで、殺すつもりで書いていたキャラが、殺すに殺せなくなり、結果生き残ってしまうわけです。
ジレンマですね。
でも萌えキャラを殺すときにはあまり躊躇を感じたことはないです。
あいつら死んだ方が絶対面白い。
うわああ萌えキャラを大量に登場させてズッコンバッコン殺しまくる話が書きたいよおおお!!
これはドーキンスと対立するわけだ。
グールドの主張は歴史の偶発性だ。
たとえば白亜紀の巨大隕石衝突によって恐竜は絶滅し、かわりに哺乳類が繁栄した。
しかし、哺乳類の繁栄は必然だったのか?
哺乳類ではなく鳥類が繁栄してもよかったのではないか?
必然であるというためには実際にそうあったという事実だけでは足りない。
哺乳類が実際に繁栄する以前の段階からその結果を予測できなければならない。
だが、哺乳類と鳥類の形態や生理機能、その他さまざまな特性を比較するかぎり、その勝敗は必ずしも決定的ではなかった。
もう一度歴史をやり直したのなら鳥類が繁栄することも十分あり得た。
こうして哺乳類が勝利したからこそ我々は後知恵でふさわしい物語を作り出すことができるが、鳥類が繁栄していた場合も同じようにふさわしい物語を捏造しているだろう。
たとえばベルグマンの法則のように、体重と表面積の比から寒冷地に棲む動物ほど体重が大きいというような、自然法則に根ざした進化も当然あり得る。
だが細目を見るならば歴史は偶然に支配されている。
過去の影を引きずる、という表現もある。
これがグールドの主張だ。
確かに一理ある。
しかし批判は可能だ。
というより、むしろ批判を待ち構えているようにさえ思える。
グールドの主張における問題点、それは偶然であることは証明できないことだ。
必然は証明できても偶然は証明できない。
ただ必然であることが証明できないとき暫定的に偶然と呼ぶだけだ。
『ユーザーイリュージョン』の言葉を借りるなら、「秩序であることは証明できるがランダム性は証明できない」。
ルーレットは一般にランダムの代名詞のように考えられているが、実際には回転板の速度・加速度、玉を弾く速度や角度、重力加速度や空気抵抗などのあらゆる物理的な情報が事前にわかっていればルーレットの結果は原理的に予測できる。
(それがわからないから我々の目にはルーレットはランダムに見える)
『ワンダフル・ライフ』にもあった、科学の反証可能性についてを引用すれば、「仮説というのはまったく間違っているか、おそらく正しいか」の二択だ。
グールドの歴史の偶発性という考え方はどっちつかずではないか。
「まったく間違っている」と証明されるまで「おそらく正しい」。
積極的に「おそらく正しい」と主張するのではなく、その態度は消極的だ。
つまり反証のしようがないのだ。
おそらくこれは彼自身も自覚している矛盾だろう。
無矛盾であるよりは議論を引き起こすことを彼は選択した。多分。
グールドの主張は警告としては意義深いが、少々悪魔の証明のきらいがある。
と、彼の主張にはいくらか批判はあるが、本書で取り上げる歴史科学や古生物学の方法、バージェス動物群の異質さなどは非常に興味深く、一読に値する。
また、科学者の姿を神格化もせず、しかし貶めもしない彼の態度は素直に評価できる(ドーキンスは少々科学者を神格化するきらいがある)。
上下逆さまに復元されたハルキゲニアかわいい!
『ドーキンスVSグールド』と併せて読めばバランスがとれるだろう。
グールドの主張は歴史の偶発性だ。
たとえば白亜紀の巨大隕石衝突によって恐竜は絶滅し、かわりに哺乳類が繁栄した。
しかし、哺乳類の繁栄は必然だったのか?
哺乳類ではなく鳥類が繁栄してもよかったのではないか?
必然であるというためには実際にそうあったという事実だけでは足りない。
哺乳類が実際に繁栄する以前の段階からその結果を予測できなければならない。
だが、哺乳類と鳥類の形態や生理機能、その他さまざまな特性を比較するかぎり、その勝敗は必ずしも決定的ではなかった。
もう一度歴史をやり直したのなら鳥類が繁栄することも十分あり得た。
こうして哺乳類が勝利したからこそ我々は後知恵でふさわしい物語を作り出すことができるが、鳥類が繁栄していた場合も同じようにふさわしい物語を捏造しているだろう。
たとえばベルグマンの法則のように、体重と表面積の比から寒冷地に棲む動物ほど体重が大きいというような、自然法則に根ざした進化も当然あり得る。
だが細目を見るならば歴史は偶然に支配されている。
過去の影を引きずる、という表現もある。
これがグールドの主張だ。
確かに一理ある。
しかし批判は可能だ。
というより、むしろ批判を待ち構えているようにさえ思える。
グールドの主張における問題点、それは偶然であることは証明できないことだ。
必然は証明できても偶然は証明できない。
ただ必然であることが証明できないとき暫定的に偶然と呼ぶだけだ。
『ユーザーイリュージョン』の言葉を借りるなら、「秩序であることは証明できるがランダム性は証明できない」。
ルーレットは一般にランダムの代名詞のように考えられているが、実際には回転板の速度・加速度、玉を弾く速度や角度、重力加速度や空気抵抗などのあらゆる物理的な情報が事前にわかっていればルーレットの結果は原理的に予測できる。
(それがわからないから我々の目にはルーレットはランダムに見える)
『ワンダフル・ライフ』にもあった、科学の反証可能性についてを引用すれば、「仮説というのはまったく間違っているか、おそらく正しいか」の二択だ。
グールドの歴史の偶発性という考え方はどっちつかずではないか。
「まったく間違っている」と証明されるまで「おそらく正しい」。
積極的に「おそらく正しい」と主張するのではなく、その態度は消極的だ。
つまり反証のしようがないのだ。
おそらくこれは彼自身も自覚している矛盾だろう。
無矛盾であるよりは議論を引き起こすことを彼は選択した。多分。
グールドの主張は警告としては意義深いが、少々悪魔の証明のきらいがある。
と、彼の主張にはいくらか批判はあるが、本書で取り上げる歴史科学や古生物学の方法、バージェス動物群の異質さなどは非常に興味深く、一読に値する。
また、科学者の姿を神格化もせず、しかし貶めもしない彼の態度は素直に評価できる(ドーキンスは少々科学者を神格化するきらいがある)。
上下逆さまに復元されたハルキゲニアかわいい!
『ドーキンスVSグールド』と併せて読めばバランスがとれるだろう。
『海の底』よりは面白かった。無駄も少ない。
こっちのがあとの作品だろうから上達したってことになるのかな?
テンポも良かったし読みやすかった。海が数日に対し空は数ヶ月くらいの話だからかな。
でも、突っ込みどころや不満点は多いなー。
まずキャラ付けが安易すぎる。
どいつもこいつも親が死んだくらいで人生左右されすぎだろ。
「肉親を失ったものが復讐に走る」てのは「身障者は健気」と同じような偏見を感じる。
瞬にしても真帆にしても、「事故で親を失った」というキャラ付け以上の「正体」がない。
趣味は? 思想は? 経済状態は? 将来の夢は? そういうのが一切感じられない。
他にすることねーのかよって感じ。
夢で出てきて起きたら泣いてるくらいは普通によくあるけど、言ってしまえばそれだけ。
たとえば、「フェイク=【白鯨】=親を事故死させた原因」てのがわかったときの瞬の態度。
今まで仲良くしてた未確認生物にいきなり「お前はもう要らない」なんて言わないよ!
なにこれどういうこと。一般に作者や読者はこういう感情の変化を「自然」で「普通」だと思ってるの?
感情の変化が急すぎる。
まず「え? マジで?」ってなって、それから理屈で考えて「言われてみりゃそうかもしれない」って冷静になって、はじめて「フェイク=【白鯨】=親を事故死させた原因」という事実を受け入れるのが普通の感情の流れじゃなかろうか。
感情的・直観的には「フェイク」と「親の仇」は簡単には結びつかない。
理屈で考えてはじめて認められるわけだから、それが怒りや憎しみなどの激情に繋がることはない。
と、僕は思うのだけれど、実際に同じ状況になったことはないからわかんにゃい。
もし僕が瞬の立場だったら伏線回収の手際の良さに感動するのに忙しいかな。
関連して、「セーブ・ザ・セーフ」という組織にまるでリアリティを感じない。
要するに募金詐欺やゴネ得の遺族団体……なんだよね?
でも、その代表者(?)である真帆がそういう利権とかに無関心で【白鯨】を本気で憎んでる感じがすげー嘘くさくてならない。
多分、主人公(空自や高巳)の対立勢力に無理矢理なにかしらの正当性を与えて倫理的なバランスを調整して「正義VS正義(笑)」を演出してるつもりなんだろう。
『コンタクト』でもそうだし、こういう事件が起きたらこの手の団体が発生するのは予想できるが、物語の主役にはなれないと思うんだよね。
「邪魔だけれど排除するわけにもいかない脇役」がふさわしいポジションだと思う。
主人公の反対勢力は必要だけど、もっと政治的な動機を持ってきて欲しかった。
細かいところで言えば、「電波を受信して言葉を覚えた」という設定。
デコードの仕方もわからんのによう言語として認識できたな……。
詳しいことは知らないけど、携帯やらラジオやらで通信の規格はいろいろ違うはず。
たとえばモールス信号と現代通信はやっぱり全然違うし。
言語だけでなく映像や画像の通信だってあるし。
暗号を解読するにしても元の言語がわからないことにはどうにもならなそうなものだが。
古代エジプトの言語を解読するようなものなのかしら。
でも、それにしても現在残ってる言語を参考にしたり……とかするよね?
まあこのへんはハードSFじゃあるめえしブラックボックスで結構だと思うけど。
いや待て、そもそも生来単一の個体のみしか存在せず集団という概念を持たなかった【白鯨】がどうして他者との情報伝達手段である言語という概念を理解できたのか……うん、好意的にスルーしよう。
逆に言えば、中途半端に【白鯨】誕生秘話みたいなくだりは入れるべきじゃなかった。
だってあれ意味がわからなすぎるもん。
進化史っぽい書き方してるけど、【白鯨】はダーウィニズム的に進化したんじゃなくてデジモンやポケモンみたいな感覚で「進化」したってこと?
中途半端な知識で書いてる感がありあり伝わってきて、無理しなくてもいいのよ、って思った。
とまあ、gdgd書いたけど、ファーストコンタクトものとして十分エンターテイメントしてて良かったと思うよー。
特に新しいアイデアや奇抜な発想は見られなかったけど。
「未知なるものとの対話」って感じはそれなりにワクワクする描写ができてたと思う。
こっちのがあとの作品だろうから上達したってことになるのかな?
テンポも良かったし読みやすかった。海が数日に対し空は数ヶ月くらいの話だからかな。
でも、突っ込みどころや不満点は多いなー。
まずキャラ付けが安易すぎる。
どいつもこいつも親が死んだくらいで人生左右されすぎだろ。
「肉親を失ったものが復讐に走る」てのは「身障者は健気」と同じような偏見を感じる。
瞬にしても真帆にしても、「事故で親を失った」というキャラ付け以上の「正体」がない。
趣味は? 思想は? 経済状態は? 将来の夢は? そういうのが一切感じられない。
他にすることねーのかよって感じ。
夢で出てきて起きたら泣いてるくらいは普通によくあるけど、言ってしまえばそれだけ。
たとえば、「フェイク=【白鯨】=親を事故死させた原因」てのがわかったときの瞬の態度。
今まで仲良くしてた未確認生物にいきなり「お前はもう要らない」なんて言わないよ!
なにこれどういうこと。一般に作者や読者はこういう感情の変化を「自然」で「普通」だと思ってるの?
感情の変化が急すぎる。
まず「え? マジで?」ってなって、それから理屈で考えて「言われてみりゃそうかもしれない」って冷静になって、はじめて「フェイク=【白鯨】=親を事故死させた原因」という事実を受け入れるのが普通の感情の流れじゃなかろうか。
感情的・直観的には「フェイク」と「親の仇」は簡単には結びつかない。
理屈で考えてはじめて認められるわけだから、それが怒りや憎しみなどの激情に繋がることはない。
と、僕は思うのだけれど、実際に同じ状況になったことはないからわかんにゃい。
もし僕が瞬の立場だったら伏線回収の手際の良さに感動するのに忙しいかな。
関連して、「セーブ・ザ・セーフ」という組織にまるでリアリティを感じない。
要するに募金詐欺やゴネ得の遺族団体……なんだよね?
でも、その代表者(?)である真帆がそういう利権とかに無関心で【白鯨】を本気で憎んでる感じがすげー嘘くさくてならない。
多分、主人公(空自や高巳)の対立勢力に無理矢理なにかしらの正当性を与えて倫理的なバランスを調整して「正義VS正義(笑)」を演出してるつもりなんだろう。
『コンタクト』でもそうだし、こういう事件が起きたらこの手の団体が発生するのは予想できるが、物語の主役にはなれないと思うんだよね。
「邪魔だけれど排除するわけにもいかない脇役」がふさわしいポジションだと思う。
主人公の反対勢力は必要だけど、もっと政治的な動機を持ってきて欲しかった。
細かいところで言えば、「電波を受信して言葉を覚えた」という設定。
デコードの仕方もわからんのによう言語として認識できたな……。
詳しいことは知らないけど、携帯やらラジオやらで通信の規格はいろいろ違うはず。
たとえばモールス信号と現代通信はやっぱり全然違うし。
言語だけでなく映像や画像の通信だってあるし。
暗号を解読するにしても元の言語がわからないことにはどうにもならなそうなものだが。
古代エジプトの言語を解読するようなものなのかしら。
でも、それにしても現在残ってる言語を参考にしたり……とかするよね?
まあこのへんはハードSFじゃあるめえしブラックボックスで結構だと思うけど。
いや待て、そもそも生来単一の個体のみしか存在せず集団という概念を持たなかった【白鯨】がどうして他者との情報伝達手段である言語という概念を理解できたのか……うん、好意的にスルーしよう。
逆に言えば、中途半端に【白鯨】誕生秘話みたいなくだりは入れるべきじゃなかった。
だってあれ意味がわからなすぎるもん。
どうやって得たんだよwwwwそして【白鯨】は「飛ぶ」という概念を得た。
進化史っぽい書き方してるけど、【白鯨】はダーウィニズム的に進化したんじゃなくてデジモンやポケモンみたいな感覚で「進化」したってこと?
中途半端な知識で書いてる感がありあり伝わってきて、無理しなくてもいいのよ、って思った。
とまあ、gdgd書いたけど、ファーストコンタクトものとして十分エンターテイメントしてて良かったと思うよー。
特に新しいアイデアや奇抜な発想は見られなかったけど。
「未知なるものとの対話」って感じはそれなりにワクワクする描写ができてたと思う。
プロフィール
@aebafuti からのツイート
公開中のゲーム作品
『ロリ巨乳の里にて』
パイズリセックスRPG。
『幽獄の14日間』
リソース管理型脱出RPG。
『カリスは影差す迷宮で』
仲間を弱らせて殺す遺跡探索RPG。
『黒先輩と黒屋敷の闇に迷わない』
探索ホラー風セクハラゲーム。
『英雄候補者たち』
特に変哲のない短編RPG。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
メタメタフィクションノベルゲーム。
『或る魔王軍の遍歴』
「主人公補正」によって哀れにも敗れていくすべての悪役に捧ぐ。
『ドアによる未来』
「どこでもドア」はいかに世界に影響を及ぼし、人類になにをもたらすのか。



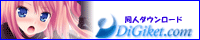
パイズリセックスRPG。
『幽獄の14日間』
リソース管理型脱出RPG。
『カリスは影差す迷宮で』
仲間を弱らせて殺す遺跡探索RPG。
『黒先輩と黒屋敷の闇に迷わない』
探索ホラー風セクハラゲーム。
『英雄候補者たち』
特に変哲のない短編RPG。
『Merry X'mas you, for your closed world, and you...』
メタメタフィクションノベルゲーム。
公開中の小説作品
「主人公補正」によって哀れにも敗れていくすべての悪役に捧ぐ。
『ドアによる未来』
「どこでもドア」はいかに世界に影響を及ぼし、人類になにをもたらすのか。


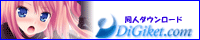
新着記事
2021 - 10 - 24
2020 - 12 - 03
2020 - 10 - 03
2020 - 06 - 30
2020 - 04 - 29
カテゴリー
アーカイブ
検索
新着コメント
[02 / 26 by 白蛇]
[02 / 26 by 白蛇]
[05 / 21 by 西 亮二]
[12 / 15 by NONAME]
[07 / 04 by アーミー]
ブックマーク
連絡先
aebafuti★yahoo.co.jp(★を@に変えて送ってください)
カウンター

